KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?
将来の夢は?
5名の学生たちが本音で語ります。

渡邊 秀行
日本
修士2年
参加プロジェクト:Creative Industry

下川 七菜子
日本
修士2年
参加プロジェクト:Policy Project

森山 紗江
日本
修士2年
参加プロジェクト:ITOMA

菊池 美咲
日本
修士1年
参加プロジェクト:Global Education

藤本 隆寛
日本
修士2年
参加プロジェクト:Network Media
―KMDに入学した理由を教えてください。
渡邊: 現在、外資系企業で働いているのですが、もっと自分の幅を広げたいと考えていたときにKMDを知りました。Creative Industryを選んだ理由は、課題に対して新しいアプローチで解決を模索するというリアルプロジェクトの内容が自分の取り組みたいもの重なると感じたからです。
下川: 大学生のときから母とヴィーガンレストランを運営しています。「将来、プラントベースの食事が日々の選択肢の一つとして当たり前の食習慣になってほしい」という思いで試行錯誤するなか、もっと新しい感覚を取り入れたいと考えはじめたときにKMDと出会いました。やりたいことを応援してくれる環境が整っていて、入学してから楽しく研究を続けています。
森山: 7年ほど会社員として働きながら、個人的にイベント企画の活動を続けていました。そのなかで空間デザインに興味を持つようになり、KMDの存在を知りました。リアルプロジェクト閑では、モノや空間を通して人の体験を生み出すことに軸を置いてさまざまな研究をしています。
菊池: 学部では土木工学を学び、大学院では構造設計に進む予定でした。自分がこれから本当に何をやりたいのかを考え直したとき、人と人をつなげるものをつくりたいと思い、改めてデザインについて学ぶためにKMDに来ました。
藤本: 大学の卒業論文で、世界の有名画家の作品をデジタル化し、それらをバラバラに分解してもその人の作品であると認識できるかどうかという実験しました。そのとき担当教授から美術大学の修士課程かKMDを奨められて、KMDを選びました。


―現在のプロジェクトについて教えてください。
渡邊: リアルプロジェクトCreative Industryでは日本のさまざまな地域と協働していて、今は福井県鯖江市でのプロジェクトに参加しています。3Dプリンターやレーザーカッターなどの機材が揃うファブラボでモノづくりをしながら、その地に伝わる工芸の新しいアプローチについて研究しています。例えば、漆塗りを新解釈し、伝統技術を生かして現代に受け入れられるような商品を開発するなどです。
下川: 私はPolicy Projectで、ヴィーガン普及のために「食べる場所を増やす、プロダクトを増やす、食について考える機会を増やす」をコンセプトに研究をしています。例えば、植物肉は環境問題や食糧危機の対策として注目されていますが、ヴィーガンではない人たちをどう巻き込んでいくか、肉が好きな人でもおいしいと言ってもらえるプロダクトをつくっています。
菊池: 私も食育に興味があって、Global Educationでは小学生のいとこを連れて、三重県鈴鹿市のお茶農家に行ってフィールドワークを行いました。一緒にお茶を摘んだり、蒸したり、さまざまな工程を見学しながら、お茶づくりを学ぶ体験をして、いとこは苦手だったお茶が大好きになりました。この体験から、食育に関わるプロダクトやスペースデザインの研究を進めています。
森山: リアルプロジェクト閑のサウンドスケーププロジェクトで活動しています。ユーザーが街を歩きながら音声ガイドを聞き、その街やスポットの魅力を知るサービスに取り組んでいます。プロのツアーガイドさんに同行して、実際にどのような案内をしているのかを観察調査しながらプロトタイプに生かしています。
藤本: 実は朝起きるのが苦手で、少しでもすっきり目覚めることができないかと考えながら、睡眠の研究をしています。人間の睡眠リズムに影響を及ぼすといわれるブルーライトを活用して、メラトニンの分泌を抑制する目覚まし装置をつくりました。この装置を通じて、心拍数や部屋の明るさ、気温といったデータを取得し、目覚めと環境の相関について研究しています。
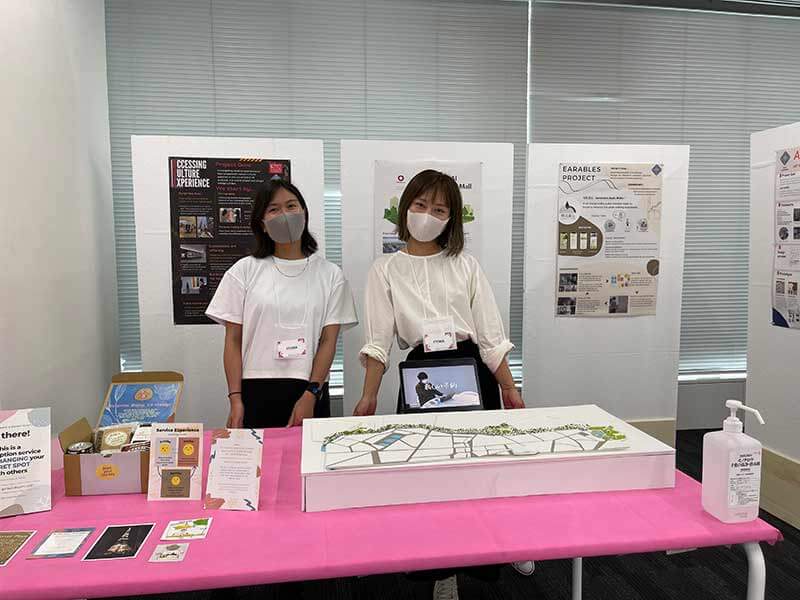

―コロナ禍での学内生活について教えて下さい。
藤本: 研究テーマを考えるとき、近くにいる人をつかまえて「これどう思う?」と感想を聞くことが大切だと思っています。コロナ禍で、研究について気軽に話し合える場が減ってしまい、悩ましかったです。今はこの生活にだんだん慣れてきて、自分たちのコミュニティを中心に工夫しながら話し合う機会も増えてきました。
下川: 「このテーマで論文を書いて、この実験をして、この時期には商品ができるのでアンケートを取って」と予定していたことが、緊急事態宣言の延長でどんどんずれ込んでしまいました。論文の提出日に商品が出せず、辛かったです。
森山: 私はコロナ禍に入学をしました。リアルプロジェクト閑ではフィールドワークとプロトタイピングが重要で、そのためには人とフィジカルに会って取り組むことが欠かせません。動けない時期もありましたが、今は申請をすれば必要な部屋や機材を使えるし、リアルとオンラインのハイブリッドな使い分けができています。
下川: ティーチングアシスタントとしてゲスト講師の講義をサポートしています。リアルの講義では学生がなかなか質問をしてくれないのが課題だったのですが、コロナ禍を機にチャットアプリを導入したところ、オンライン授業ではたくさんの質問が集まるようになりました。奇しくもコミュニケーションが活性化した部分もありますね。

―KMDに興味を持つ方々へのメッセージ
渡邊: KMDは国籍や年齢など多種多様なバッググラウンドをもつ人が集まって、さまざまな研究をしています。研究を支援してくれる環境も整っているので、入学を検討していたらぜひおすすめします。
下川: KMDはコミュニケーションを取りやすい環境で、やりたいことがある人の活動を応援し合う文化があります。やりたいことが明確な人も、自発的に動けるタイプの人も最大限活用できる場所だと思います。
森山: 私の場合、最初からやりたいことが明確にあったかというとそういうわけでもないんです。でもKMDに入学してから、さまざまなリアルプロジェクトを見ることで、興味をもてるテーマに出会うことができました。ですから「何か新しいことをやりたい」という気持ちがあれば大丈夫ですよ!
菊池: 今やりたいことが漠然としていたとしても、KMDならまわりの人が助けてくれるし、自然に道が拓けるところがあります。「何かをやりたい」というパッションさえあれば、楽しいことがきっとたくさん見つかります。
藤本: KMDの魅力は、教授や教員の専門性やネットワークを含めて、豊かな知のリソースがあることです。何かを尋ねれば「それならわかるよ、あの人を紹介できるよ」とすぐに返してくれるし、スピーディにモノづくりしたり、実験するための道具もそろっています。KMDに入る前でも入ってからでもいいので、まずは自分のまわりにどんなリソースがあるのかを知って、それを生かして「何をするか」を決めていくことが大切です。

―ありがとうございました。
※ 本記事は2021年7月に取材したものです。